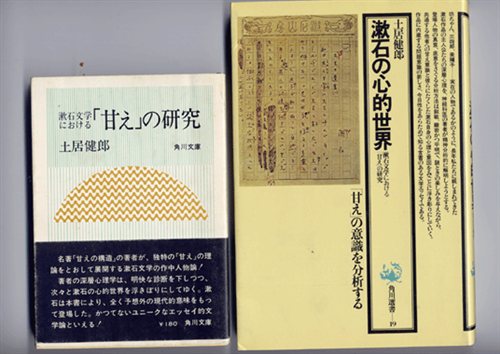<「心」(夏目漱石)に見る同性愛>
先日、新聞で土居健郎の死を知ったとき、彼の『漱石文学における「甘え」の研究』を読むことなしに今日まで来てしまったことに気がついた。土居健郎には、「甘え」の理論を漱石文学に適用した文庫本があることを知って、前々から、読んでみたいと考えていたのである。
それで、遅ればせながら、インターネット古書店で目録を調べ、以下の二冊の本を注文した。
漱石文学における「甘え」の研究
漱石の心的世界
本が届いたので調べて見たら、この二冊は題名が違うだけで、内容が同じなのだった(多少の差異あり)。通信販売で本を購入すると、この種の手違いはつきものなのである。とにかく、活字の大きな本から――「漱石の心的世界」から読み始めた。
土居健郎は、漱石の主要作品を項目別に分けて分析している。面白かったのは、「それから」の章だった。土居は、代助と平岡が同性愛的関係にあったというのである。
「それから」は、概略次のような物語だ。
代助は資産家の末子に生まれ、30になるのに未だ父親の仕送りをうけている。ニートの癖に彼は一戸を構え、婆さんと書生まで雇っているという恵まれた立場にある。そこへ学生時代の友人の平岡が、訪ねてくるのだ。彼は三千代という妻を持つ身なのに、目下失業中だった。代助は平岡夫妻と行き来しているうちに、三千代と不倫の関係になる。そのため父の怒りを買い、仕送りを断たれてしまう。かくて代助は社会の荒波の中に放りこまれ、アップアップすることになる、これが「それから」の粗筋なのだ。
代助と三千代は、以前から浅からぬ因縁があった。三千代はもともと代助の友人の妹で、二人は互いに好意を持ち合っていた。三千代の兄が病気で急死したため、三千代は孤独な身になる。こういうときにこそ、経済的に恵まれた代助が彼女を救わなければならないのに、代助は友人の平岡が三千代を愛していると告白すると、彼は平岡のために尽力し三千代を説得して二人を結びつけてやるのだ。三千代は、代助に捨てられたという思いを胸に抱きながら、平岡と結婚するのである。
「それから」を読んでいて、一番引っかかるのは、どうして代助は好意を持っていた女性を平岡に与えてしまったか、という点だった。それを土居健郎は、代助が平岡と同性愛の関係にあり、三千代よりも平岡の方を愛していたからだと説明する。なるほど、これなら、ちゃんと筋が通る。
土居の著書から、その部分を引用する。
< ・・・・・・彼女をもし本当に彼が初めから愛していたならば、友人に譲れるはずが ない。もし愛していたとしても、彼の友人に対する愛の方が遥かに大きかったからこそ 、彼女を譲ることができたのである。このことから推論できることは、代助には潜在的 な同性愛的傾向がなかったかという点である。彼が結婚して得意になっている平岡を憎 らしく思ったのも、この同性愛的傾向の表現であると解することができる。>
土居健郎は、こうした視点を、「心」にも持ち込むのだ。
「心」を読んでいて引っかかるのは、大学生の「私」が一面識もなかった「先生」に魅惑されて強引に接近し、「先生」の自宅に出入りするまでになるところだ。どう考えても、「先生」と「私」の関係は不自然なのである。「先生」は、世間に名の知れた名士などではなく、そこばくの資産を頼りに居食いしている「高等遊民」にすぎないのである。こんな中年男に惹きつけられて、後を追い回す大学生などいるだろうか。
この点を解明してくれたのは、大岡昇平の評論だった。彼は、欧米では「心」を同性愛小説として読んでいると書いている。そういえば、「先生」は自分につきまとって離れない「私」に向かって、「君は私に恋しているのだ」という場面がある。
もしかすると、夏目漱石と寺田寅彦の関係も、同性愛だったかも知れないぞと、私は思った。漱石は神経質で気むずかしい癇癪持ちだと聞かされていたが、寺田寅彦は漱石の許可を得ることなしに平気で書斎に入ってきて、室内で寝ころんだり、あくびをしたりして一時間ほどを過ごし、また黙って部屋を出て行ったそうである。寺田寅彦は、自分がそうすることを漱石によって許されていると信じており、事実、漱石は若い恋人のわがままを許す中年男のように寺田の行動を黙認していたのだ。
しかし、土居健郎は私が行ったような推論を否定している。「先生」と「私」は父子の関係で結ばれていたのであり、同性愛の関係で結ばれていたのは、「私」と「K」の方だったというのだ。そして、「先生」と「私」は父子の関係にあったと強調し、その傍証として、「先生」が「私」に残した遺書の一節をあげる。「先生」はこういっているのである。
<私の鼓動が停まった時、あなたの胸に新しい命が宿ることが出来たら満足です。>
土居は、「それから」の章で代助の愛は三千代に対するものより平岡に対するものの方が強かったと論証した。彼は「心」についても、「先生」の愛は、奥さんに対するものより、「K」に対するものの方が強かったといっている。
<・・・・・・大体彼の妻に対する愛には初めから問題が存したといっても過言ではない。彼は彼女に恋心を感じながら、いつまでも彼女の心根を疑って、中々彼女を愛する決心がつかなかった人間である。そして最後に求婚したのも愛する決心がついたというよりも、一途にKに出しぬかれまいとしたために他ならなかった。この意味で彼の根本的姿勢は同性愛的であったといわねばならないのである。>
<彼は「K」への愛故に殉死し、「私」への愛故に遺書を書き残したといってよい。しかし妻には最後まで自分の心を打ち明けず、遺書すらも見せることを欲しなかったというのは一体何を物語るのであろう。「妻が己れの過去に対してもつ記憶をなるべく純白に保存しておいてやりたい」というのは果して愛なのであろうか。>
(つづく)